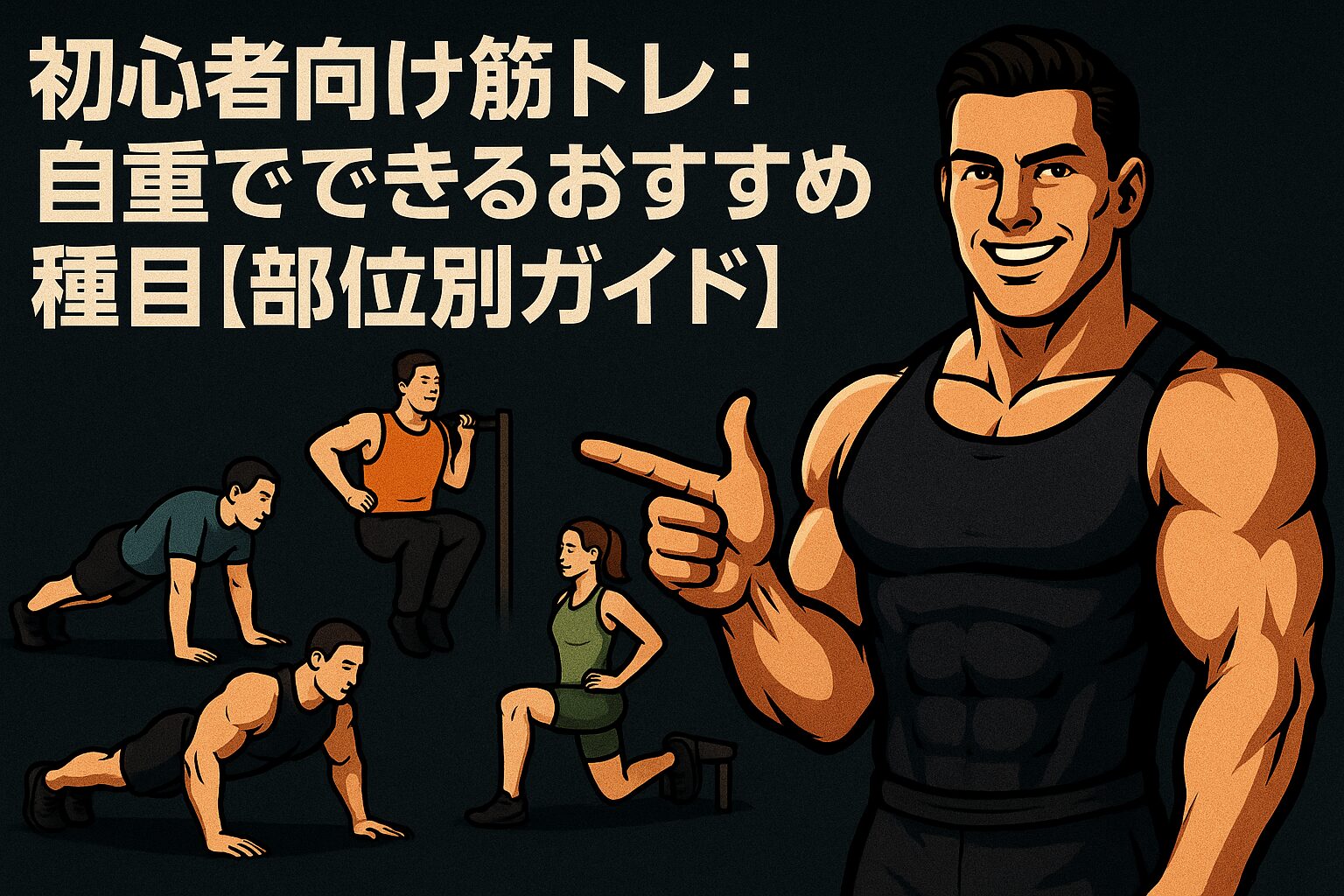筋トレを始めたいけど、「自宅で器具なしでできる効果的な種目が分からない…」「フォームが不安でケガしないか心配…」と悩んでいませんか?誰しも最初は何から手をつけていいか迷うものです。本記事では、筋トレ初心者が自重でできるおすすめ種目を部位別に紹介し、それぞれの効果や正しいフォーム、注意点を分かりやすく解説します。自宅で手軽に全身を鍛えて、理想の体づくりを始めましょう。
この記事はこんな人におすすめ:
- 筋トレ初心者で、ジムの器具なしで自重トレーニングを始めたい方
- 忙しくてジムに通えないが、自宅で効率よく部位別に筋トレしたい方
- 各種目の正しいフォームや効果を知り、安全にトレーニングしたい方
この記事でわかること
- 筋トレ初心者向けの自重でできるおすすめ種目(胸・背中・腕・肩・脚の部位別)
- 各種目の期待できる効果や鍛えられる筋肉、正しいフォームとコツ
- 怪我を防ぎ効果を高めるための注意点と科学的根拠に基づくポイント
筋力トレーニングは、世界保健機関(WHO)のガイドラインでも全身の主要筋群を週2回以上鍛えることが推奨されています。自重トレーニングであれば特別な器具が不要で、自宅でも手軽に実践できます。それでは部位別に見ていきましょう(**「初心者 自重トレーニング」「筋トレ 自重 おすすめ種目」「部位別 筋トレ」**などのキーワードも意識しながら読み進めてくださいね)。
胸の筋トレ(大胸筋):プッシュアップ・ディップス
胸筋を鍛える代表的な自重トレーニングには、プッシュアップ(腕立て伏せ)とディップスがあります。どちらも上半身の筋肉を効果的に刺激し、厚い胸板や腕力を養うのに役立つ種目です。それぞれの効果とやり方、注意点を確認しましょう。
プッシュアップ(腕立て伏せ)
プッシュアップの正しいフォーム例(体を一直線に保ち、胸を床に近づける)
期待できる効果
プッシュアップは自重筋トレの基本種目で、主に胸の筋肉(大胸筋)を鍛えます。同時に肩の三角筋や腕の上腕三頭筋(いわゆる二の腕の裏側)にも負荷がかかり、上半身を広く強化できるエクササイズです。さらに、正しいフォームで行えば腹筋や背筋など体幹や下半身の筋肉も静的に使われ、全身を連動させる運動になります。腕立て伏せは器具がいらず場所を選ばないため、いつでもどこでも実践できる手軽さも大きなメリットです。
また、プッシュアップは筋力・持久力の指標にもなり得ます。例えば、50歳代の消防士を対象にした研究では、一度に40回以上の腕立て伏せができる人は、10回未満しかできない人に比べて10年以内の心血管疾患リスクが大幅に低かったと報告されています。これは腕立て伏せが全身持久力を反映し、心肺の健康指標としても有用である可能性を示すものです。腕立て伏せを継続することで、筋力アップだけでなく健康面でのメリットも期待できるでしょう。
正しいフォーム
① 姿勢を整える(スタートポジション)
- 両手を肩幅よりやや広めに床につく
- 腕をまっすぐに伸ばし、頭からかかとまで一直線になるようにする(=プランク姿勢)
- 足は揃えるか、腰幅程度に開く
- 視線は床に向ける(首が反らないように)
- 背中が反ったり丸まったりしないよう、体を一直線にキープ
② 身体を下げる(ネガティブ動作)
- 息を吸いながら、肘をゆっくり曲げて上体を下げていく
- 肘が約90度になるまで、胸が床に触れる直前まで下げる
- お腹とお尻に力を入れることで、一直線の姿勢をキープ
- 肘は開きすぎないようにし、脇を約45度の角度に保つ(肩への負担を減らす)
③ 元の姿勢に戻る(ポジティブ動作)
- 息を吐きながら、肘を伸ばして身体を押し上げる
- 再び最初の一直線の姿勢に戻る
もし通常のプッシュアップが難しい場合は、膝つき腕立て伏せから始めるのがおすすめです。膝を床につけた状態で同様の動作を行えば、負荷が下がり初心者でも正しいフォームを習得しやすくなります。また、逆に物足りなくなってきたらゆっくり動作する、手の位置を狭くする、足を台に乗せて行う(デクラインプッシュアップ)などで負荷を上げることも可能です。スピードや角度、手幅を調整すれば、筋肉への刺激を変えることもできます。
注意点
フォームを崩さないことが何より重要です。ありがちなミスとして、腰が落ちてお尻が沈んでしまう(反り腰)、逆にお尻が上がりすぎる、肘を開きすぎる、といった点が挙げられます。フォームが崩れると鍛えたい胸や腕に効かせにくいだけでなく、腰痛や肩の怪我の原因にもなります。鏡で横からチェックするか、スマホで動画撮影するなどして、自分のフォームを確認するとよいでしょう。
また回数をこなそうとするあまり浅い腕立て伏せになるのも注意が必要です。しっかりと胸が床に近づく範囲まで下ろさないと十分な刺激が得られません。最初は回数より質を意識し、正しいフォームでできる回数を少しずつ増やしていきましょう。筋力がついて慣れてきたら、段階的に回数やセット数を増やしたり、難易度の高いバリエーションに挑戦したりすると効果的です。疲れてフォームが崩れてきたら無理に続けず切り上げる勇気も大切です。質の高い反復を積み重ね、着実に胸筋と腕力を強化していきましょう。
ディップス
期待できる効果
ディップスは大胸筋の下部に強い刺激を与えられる自重トレーニングです。平行棒や椅子の縁などを使って両腕で体を支え、肘を曲げ伸ばしする動作によって、胸の下部から肩、そして二の腕(上腕三頭筋)まで一緒に鍛えることができます。いわば「垂直方向の腕立て伏せ」とも言える種目で、胸筋に厚みを出しつつ腕も太くするのに効果的です。自重トレーニングの中では負荷が高めで、筋肥大効果も大きいメニューとされています。胸と腕を同時に鍛える複合種目として、上半身を一気に強化したい人に適したエクササイズです。そしてこのトレーニング種目は有名なボディービルダーも行っているので非常に効果が高いです。
正しいフォーム
ディップスを行うには、平行棒(ディップスタンド)があると理想ですが、なければ安定した椅子やベンチを使って代用できます。
① スタートポジションを作る
- 両手で平行棒(ディップバー)をしっかり握る
- 腕をまっすぐ伸ばし、肩の力を抜いて肩を上げないよう注意
- 足を軽く後ろに曲げて宙に浮いた状態を作る
- 頭から腰まで体を一直線に保つ
② 身体を沈める(ネガティブ動作)
- 上体をやや前傾させながら、肘をゆっくり曲げていく
- 肩の高さが肘と同じか少し下になる程度まで沈める
(目安:肘の角度が約90度) - 動作中も肩をすくめないように注意
③ 身体を押し上げる(ポジティブ動作)
- 胸と腕(特に大胸筋・上腕三頭筋)の力で体を押し上げる
- 肘を伸ばして最初の姿勢に戻る
- 上体は終始前傾姿勢をキープしておくことで、胸に効きやすくなる
椅子やベンチで行う場合(いわゆるベンチディップス)、背を向けて手をベンチの縁に置き、足を前方に伸ばして支えます。腕を伸ばしてお尻を浮かせたら、肘を曲げてお尻を床に向けて落としていきます。大胸筋下部と上腕三頭筋に効かせるには、この場合も体を軽く前傾させるのがコツです。肘が直角になるまで下げたら、腕の力で押し戻します。背中がベンチから離れすぎると負荷が逃げてしまうので、体はベンチに沿わせるように上下させましょう。
注意点
ディップスは初心者には少し難易度が高い種目です。筋力が不足している段階で無理に行おうとするとフォームが崩れやすく、特に肩関節や手首へ過度な負担がかかりがちなので注意してください。肘を深く曲げすぎて、上腕が床と平行より下になるほど沈み込むのは危険です。肩が後ろに大きく開いた姿勢になると肩関節を痛める恐れがあります。実際、肩の腱板損傷の観点からも、腰がベンチより下に落ちるような深いベンチディップスは避けるべきと指摘されています。肘は90度程度まで曲げたら止める、と覚えておきましょう。
どうしても難しい場合は、最初はベンチディップスから開始し、慣れてきたら平行棒ディップスに移行するのも手です。ベンチディップスでもきつい場合は、足を床につけたまま一部体重を支えるようにすると負荷を調整できます。逆に平行棒ディップスで物足りなくなってきたら、足にダンベルを挟む・重り付きベルトを使うなど加重してさらなる負荷をかけることも可能です。
肩に痛みを感じる場合は無理せず他の種目で代替することも検討しましょう。例えば、腕立て伏せの手幅を狭めたナロープッシュアップでも上腕三頭筋や下部胸筋は鍛えられます。安全第一で、自分の筋力レベルに応じて段階的にチャレンジしてください。
背中の筋トレ(広背筋など):懸垂・Tレイズ
背中は自重で鍛えにくい部位と思われがちですが、懸垂(プルアップ)やTレイズなど工夫次第でしっかり鍛えることができます。広背筋や僧帽筋など背中の大きな筋肉は、鍛えると姿勢改善や基礎代謝アップにもつながる重要な部位です。器具を使った懸垂と、床で行える種目Tレイズの2つを紹介します。
懸垂(プルアップ)
期待できる効果
懸垂(プルアップ)は、自重で背中の筋力を高める代表的なトレーニングです。鉄棒や懸垂バーにぶら下がり、自分の体重を引き上げる動作を繰り返すことで、主に背中の広背筋を鍛えることができます。広背筋は体の中でも大きな筋肉で、ここを鍛えると逆三角形のたくましい背中が形成されます。女性の場合はくびれがより出やすくなります。さらに懸垂では腕の上腕二頭筋(力こぶ)や前腕、肩の後部なども動員され、上半身の「引く力」を総合的に強化できます。実際、懸垂は肩甲骨周りの安定性を高め、クライミングや水泳など高い相対筋力を要するスポーツ動作のパフォーマンス向上にも役立つ多関節種目です。自重トレーニングの中でも強度が高い分、筋力アップ効果も大きいと言えるでしょう。
正しいフォーム
① 構え(スタートポジション)
- ぶら下がれるバーを用意(ドアジム、公園の鉄棒など)
- バーを肩幅よりやや広めに**順手(手のひらが前向き)**で握る
- 腕をまっすぐに伸ばし、体を完全にぶら下げる
- 肩をすくめず、肩甲骨を軽く下げて構える
- 足は軽く組むか真下に伸ばす。体が前後に揺れないよう安定させる
② 身体を引き上げる(ポジティブ動作)
- 息を吐きながら、背中の筋肉で肘を引くように身体を引き上げる
- 胸を張りながら、顎がバーの高さを超えるまで上げる
- バーに胸を近づけるような意識で引くと背中に効きやすい
- 顎がバーを超えたら一瞬静止
③ ゆっくり戻る(ネガティブ動作)
- 息を吸いながら、身体をゆっくり下ろす
- 完全に腕が伸びる直前まで戻す
- 反動は使わず、コントロールした動作を意識する
初心者の方は最初は1回もできないかもしれません。その場合はネガティブ(降下)動作から練習しましょう。椅子などを使って顎がバーの上に来る位置までジャンプや踏み台で身体を上げ、そこからゆっくりとぶら下がる姿勢に戻る動作を繰り返します。降りるのに慣れて筋力がついてきたら、自力での引き上げに挑戦してみてください。また、市販のトレーニングチューブ(ゴムバンド)を足にかけてアシスト懸垂を行うと、体重の一部をバンドが支えてくれるため初心者でも取り組みやすいです。フォームとしては、体を揺らして反動で上がるキッピング動作は控え、ゆっくり確実に広背筋を使う意識を持ちましょう。
注意点
懸垂は体重がそのまま負荷になるため、他の種目に比べて難易度が高いです。無理に繰り返すと腕や肘を痛める可能性もあるので、最初はネガティブ動作やゴムバンドの補助を用いて筋力を養ってください。握力が先に疲れてしまうことも多いので、リストストラップを使ったり、途中でぶら下がり直して握りを整えたりしても構いません。
また懸垂は背中に効かせる感覚を掴むのが難しい種目でもあります。腕ばかりで引いて背中の筋肉を使えていないケースもあるので、動作の初めに肩甲骨を下制(肩を下げる)してから肘を引くように意識すると広背筋に刺激を入れやすくなります。もし自宅に懸垂バーがない場合は、テーブルの縁を握って身体を引き上げる**斜め懸垂(インバーテッドロー)**などでも代用可能です。いずれにせよ、フォームを大切にして少しずつ回数を増やし、背中全体の筋力アップと引き締めを図りましょう。
Tレイズ
期待できる効果
Tレイズは床にうつ伏せになって行う自重の背筋トレーニングで、器具なしで広背筋を集中的に鍛えられる種目です。
うつぶせになって両腕を真横に広げてアルファベットの「T」の字を作り、上体ごと反らせて背筋に負荷をかけます。主に背中の中央〜上部にかけて効き、姿勢を支える僧帽筋や肩甲骨周りの筋肉にも刺激が入ります。特に広背筋下部や菱形筋、脊柱起立筋といった筋群に有効で、猫背の改善や姿勢矯正にも役立つエクササイズです。懸垂のように大きな負荷はありませんが、その分初心者でも取り組みやすく、背中の筋肉を意識して目覚めさせるのに適した種目と言えるでしょう。
正しいフォーム
まず床にうつ伏せ(伏せ腹)になり、額を床につけてリラックスします。両腕を肩の高さで真横に広げて手のひらは床向きにします(身体で“T”の字を作る形)。足は軽く開いておくと安定します。この姿勢から、背中の筋肉を使って上半身を反らせていきます。腕は広げたまま肩甲骨を寄せるようにして、胸を床から浮かせましょう。上げられるところまで上げたら1秒静止し、背筋の収縮を感じます。ゆっくりと元のうつ伏せ姿勢に戻り、これを繰り返します。呼吸は上体を上げる時に息を吐き、下ろす時に吸います。
動作中は腕や首の力に頼らないことがポイントです。腕はあくまで広げたまま固定し、手で床を押したりしないようにします。目線はやや斜め前を向けておくと胸を張りやすくなります。勢いをつけず背中の力だけで静かに反らせることで、狙った広背筋にしっかり刺激を与えられます。回数は15〜20回程度を目安に、じわじわと効かせていきましょう。
注意点
腰痛がある方は無理のない範囲で行い、痛みを感じたら中止してください。上体を反らす種目なので、腰椎に違和感が出る場合は反らせる高さを小さく調整しましょう。床が硬いと腰骨や胸が痛くなる場合もあるため、ヨガマットを敷くか厚めのバスタオルを敷いて行うと良いです。
また、Tレイズは動きが小さい分「効いているのか分かりにくい」と感じるかもしれません。そんな時は上体を上げきった所で2〜3秒キープする、あるいは動作をゆっくり行うようにしてみてください。筋肉への負荷が高まり効果が実感しやすくなります。慣れてきたら回数を増やしたり、ダンベル等の軽い重りを手に持って行うことでさらに負荷を追加することも可能です。背中の筋肉は意識しづらい部位ですが、コツコツ鍛えていけば確実に姿勢が良くなり日常動作も楽になります。まずはフォーム習得を優先し、焦らず取り組みましょう。
腕の筋トレ(上腕二頭筋・三頭筋):トライアングルプッシュアップ・パームカール
腕の筋肉は見た目にも分かりやすく、鍛えると力こぶが盛り上がったり二の腕が引き締まったりします。自重で腕を鍛えるには、上腕三頭筋(二の腕裏)狙いのトライアングルプッシュアップと、上腕二頭筋(力こぶ)狙いのパームカールがおすすめです。それぞれ器具なしで腕を太く強くする効果が期待できます。
トライアングルプッシュアップ(ダイヤモンド腕立て伏せ)
期待できる効果
トライアングルプッシュアップは、手の親指と人差し指で三角形(ダイヤモンド)の形を作って行う腕立て伏せです。手幅を狭くして行うことで上腕三頭筋に強い負荷がかかり、二の腕を集中して鍛えることができます。通常の腕立て伏せに比べ可動域が広がり、筋肉への刺激も大きくなるため「きつい」と感じる人が多いですが、その分上腕三頭筋を効率よく太くする筋トレとして知られています。大胸筋や三角筋などにも負荷は入りますが、メインターゲットは二の腕です。二の腕を引き締めたい女性から、太くたくましい腕を作りたい男性まで、幅広く取り組める種目でしょう。
正しいフォーム
① 姿勢を整える(スタートポジション)
- 床に手をつき、親指と人差し指をくっつけて三角形(ダイヤ型)を作る
- 手の位置は胸の真下あたりに来るようにセット
- 足をまっすぐ伸ばして揃える
- 頭からかかとまで一直線を保ち、プランク姿勢を作る
- 視線は床に向け、体幹とお尻に力を入れて安定させる
② 身体を下げる(ネガティブ動作)
- 息を吸いながら、肘を曲げてゆっくりと身体を下ろす
- 肘は体の横ではなく、やや後方に向かって曲げるイメージで
- 脇を締めるように動かすことで、上腕三頭筋(二の腕)に効きやすい
- 胸が手に触れる直前まで下ろす(深さを確保)
③ 身体を押し上げる(ポジティブ動作)
- 上腕三頭筋を使って身体を押し上げる
- 肘を伸ばして元の姿勢に戻るが、肘はロックしない(完全に伸ばし切らない)
- 筋肉の緊張を保ったまま、次の反復へ
フォーム中は、身体が左右に傾きやすいので注意します。手の形が特殊なため手首に負担を感じる場合は、握りこぶしで行うかプッシュアップバーを使用するのも有効です。通常より負荷が高い分、フォームの乱れも起きやすいので、少ない回数でも丁寧に行うことを心がけてください。
注意点
トライアングルプッシュアップは通常の腕立て伏せより難易度が高めです。無理にフルレンジで行おうとしてフォームが崩れると、肘や手首を痛めかねません。最初は膝をついた状態で行う膝つきダイヤモンドプッシュアップから始め、慣れてきたら膝を浮かせる正規の姿勢に移行しましょう。三角形に組んだ手が滑らないよう、手の平をしっかり床に密着させることも大切です。
また、動作中に肘が外側へ開いてしまうと負荷が分散しやすくなります。肘はできるだけ体側に向け、上腕三頭筋が伸び縮みしている感覚を意識しましょう。きついからと途中でお尻が上がってしまうのもNGです。頭から膝(足)までが一直線になる姿勢を維持してください。回数は最初は5~10回程度でも構いません。上腕三頭筋に十分効かせられれば少ない回数でも効果は高いです。ゆくゆくは膝つき無しで20回以上できるようになると、かなりの腕力がついている証拠です。その域に達したら、さらに高度な片手のプッシュアップなどにも挑戦できるでしょう。
パームカール
期待できる効果
パームカールは器具を使わずに上腕二頭筋(力こぶ)を鍛えられるユニークな種目です。その名の通り「Palm(手のひら)でCurl(巻き上げる)」動作をするトレーニングで、片腕の手のひらをもう一方の手で押さえ、自己抵抗によってカール動作を行います。要するにもう片方の腕をダンベル代わりにして力こぶを鍛える方法です。ダンベルが無くても逆の手を重りにできますから、家でもジムでも出先でも場所を問わず実施できるのが魅力ですotokomaeken.com。さらに自分で抵抗を加減できるので、限界まで追い込みやすいというメリットもありますotokomaeken.com。上腕二頭筋の中でも特に内側(短頭)に効かせることができ、力こぶのピークを高く盛り上げるのに効果的と言われますcolumn.valx.jp。
正しいフォーム
① 構えの姿勢をとる
- 鍛えたい方の腕(例:右腕)の肘を軽く曲げて、拳を握る
- このとき、**手の甲が上を向くように(順手)**して構える
- 反対側の手(例:左手)で、右手首の上を上から押さえる
② 拮抗させながら肘を曲げる(力こぶを作る動作)
- 右腕で拳を肩へ引き寄せるように曲げる(カール動作)
- 同時に、左手で適度に抵抗をかけて、動作をゆっくりにする
- 自分の両腕で綱引きをしているような状態を作る
- 右肘を完全に曲げきるところまで持ち上げたら一瞬静止
③ 拮抗させながら肘を伸ばす(ネガティブ動作)
- 左手で**継続的に押し返す力(抵抗)**をかけながら、
右腕をゆっくり伸ばして元の姿勢に戻す - 筋肉の緊張を保ちながら、フォームを崩さずゆっくり行う
④ 反復と左右の切り替え
- これで1回。同様の動作を10回前後繰り返す
- 終わったら、左右の腕を入れ替えて反対側も同様に行う
ポイントは、鍛える側の肘が身体の横から動かないよう固定することです。肘が前後にブレると負荷が抜けやすいため、脇を軽く締めて肘の位置を意識しましょう。また、拳を巻き上げる際に反動を使わないことも重要です。勢いに頼ると肘関節に負担がかかる恐れもあります。常に上腕二頭筋の収縮を感じながら、ゆっくり丁寧に上下させてください。抵抗の強さは自分で調節できます。最初は軽めに押さえ、慣れてきたら強く押さえて負荷を高めるなど、自由自在に強度を変えられるのがパームカールの良いところです。
注意点
慣れないうちは、つい呼吸を止めて力んでしまいがちです。力を入れる局面(肘を曲げる時)で息を吐き、伸ばす時に吸うリズムを心掛けてください。自重ゆえに負荷が軽すぎると感じる場合は、動作をゆっくり行ったり片腕ずつ連続で行って追い込む回数を増やすと効果的です。逆に負荷が強すぎてフォームが崩れる場合は抵抗を緩めましょう。
左右の腕で筋力差があることも多いので、弱い方の腕に合わせてトレーニングすることも大切です。例えば右腕の方が弱ければ、右腕で限界まで行った回数と同じだけ左腕も行い、左右差を是正していきましょう。最後に、手首に痛みを感じる場合は無理せず中止してください。自重とはいえ互いに力を掛け合うため関節にはそれなりにストレスがかかります。違和感があれば休息をとり、問題がなければ再開するようにします。以上の点に注意しながら続ければ、自宅でも十分に力こぶを鍛え上げることが可能です。
肩の筋トレ(三角筋):パイクプッシュアップ・ベンチディップス
肩の筋肉(特に三角筋)は、上半身を逆三角形に見せるために重要な部位です。ここでは、自重で肩周りを鍛えられるパイクプッシュアップとベンチディップスを紹介します。パイクプッシュアップは肩の前部・中部に刺激を与え、ベンチディップスは肩周りを支える筋肉と二の腕を同時に鍛えます。肩の大きな筋肉は基礎代謝も高く、鍛えれば「痩せ効果」と「かっこいい体型づくり」の一石二鳥が狙えます。
パイクプッシュアップ
期待できる効果
パイクプッシュアップはお尻を高く突き上げた倒立に近い姿勢で行う腕立て伏せで、主に肩の三角筋を鍛える種目です。腕立て伏せの体勢から腰を持ち上げて身体を逆V字型(お尻が天井に向く形)にし、この状態で腕の曲げ伸ばしをします。これにより重心が腕と肩に移り、肩の前部と中部に強い負荷がかかります。まるで簡易的な倒立腕立て伏せのようなもので、器具なしで肩を重点的に鍛えられる貴重な自重トレーニングです。
三角筋は肩関節を覆う大きな筋肉で、前部・中部・後部の3つのパートに分かれています。パイクプッシュアップでは特に前部(フロント)と中部(サイド)に刺激が入るため、肩の厚みと横幅を出すのに効果的です。肩の筋肉が発達すると、身体の上辺が広がりウエストとの対比で逆三角形のシルエット(いわゆる「逆三体型」)が強調されます。そのため、パイクプッシュアップは見た目のスタイル向上と脂肪燃焼効果を両立できる一石二鳥の種目とも言われます。肩周りを引き締めたい女性にも、肩幅を広くたくましくしたい男性にもメリットのあるトレーニングでしょう。
正しいフォーム
① 姿勢を整える(スタートポジション)
- 床に四つん這いになり、腕を肩幅程度に開いて手をつく
- 足は腰幅程度に開き、つま先を立てる
- 膝を伸ばしてお尻を天井に突き上げるように体を持ち上げる
- 頭から手首まで一直線、腰からかかとまで一直線になるようにして
体全体で逆V字(「∧」)の形を作る
② 身体を下ろす(ネガティブ動作)
- 肘を曲げながら、ゆっくりと頭頂部を床に近づけるように上体を下ろす
- 動作中は背中と腕、脚をしっかり伸ばしたまま
- 頭が床すれすれになるまで下げたら一瞬静止
③ 身体を押し上げる(ポジティブ動作)
- 肩の筋肉(特に三角筋)を意識して、上体を押し戻す
- お尻を天井に突き上げる元の「∧」の姿勢に戻る
④ 繰り返す
- 動作をゆっくり丁寧に繰り返す(10回前後が目安)
- 反動は使わず、フォームを重視して行う
フォームのコツは、動作中に肘を横に張りすぎないことです。肘が外に大きく開くと負荷が分散し、肩よりも僧帽筋や腕に逃げてしまいます。肘はやや後方に向けて、肩に効いているのを感じながら上下しましょう。また、お尻の位置はできるだけ高く保ち、かかとは浮いても構いません。視線は手と手の間を見るようにすると自然な姿勢が保てます。深く下ろすのが難しい場合は、可動域は無理せずできる範囲でOKです。フォームに慣れてきたら徐々に深くしていきましょう。
注意点
パイクプッシュアップは肩に高負荷がかかる反面、不安定な姿勢で行うためバランスを崩しやすいです。頭から突っ込むような形になるので、初めは壁に向かって行うと安心です(万一バランスを崩しても壁が受け止めてくれるため)。首に負担が集中しないよう、手でしっかり体重を支えて腕・肩で動作する意識を持ちましょう。顎を引きすぎて頭を下げると血が上りやすいので、適度に顎は引かず前方を見ると良いです。
肩関節に痛みがある場合は無理をしないでください。深く下げすぎず浅めの動作から様子を見ましょう。なお、パイクプッシュアップが簡単にできるようになったら、次のステップは**倒立腕立て伏せ(ハンドスタンドプッシュアップ)**です。壁倒立から行う腕立て伏せは非常に高負荷ですが、パイクで培った肩力を更に伸ばすことができます。そこまで視野に入れつつ、まずはパイクプッシュアップで安全に肩の筋力アップを図ってください。
ベンチディップス
期待できる効果
ベンチディップスは先に紹介したディップスの応用で、椅子やベンチに手をついて行う種目です。主に鍛えられる筋肉は腕の上腕三頭筋ですが、同時に肩の筋肉である三角筋前部や、さらには背中の広背筋にも刺激が入りますufit.co.jp。自重で上腕三頭筋を追い込める数少ない種目であり、二の腕を効率よく引き締めるエクササイズとして女性にも人気がありますufit.co.jp。肩の筋肉そのものを大きく育てる目的というよりは、肩周りを含む上半身裏側の引き締め・筋持久力アップに役立つ種目と言えるでしょう。
正しいフォーム
① 準備(スタートポジション)
- 安定した椅子やベンチを用意する
- ベンチに背を向けて立ち、両手を肩幅に開いて縁を握る
- 指先は前方(身体と同じ方向)に向ける
- 足を前に伸ばしてかかとを床につける
- 腕を伸ばしてお尻をベンチから浮かせる(これがスタート姿勢)
② 身体を下ろす(ネガティブ動作)
- 息を吸いながら、肘をゆっくりと曲げてお尻を床方向に下げる
- 太ももが床と平行になるか、少し高い位置で止める
- 背中は丸めず、まっすぐに保ったまま垂直に上下するよう意識
③ 身体を押し上げる(ポジティブ動作)
- 息を吐きながら、肘を伸ばして元の姿勢に戻る
- 肘を伸ばしきる直前で一瞬静止し、筋肉の緊張をキープする
④ 繰り返す
- 上記の動作を10〜15回程度を目安に行う
- 負荷を上げたい場合は脚を台に乗せたり、重りを膝に置く
この際、背中はベンチに近づけたまま上下動するのがポイントです。お尻が遠くに離れてしまうと刺激が逃げてしまうので、背もたれに沿って上下するイメージを持ちます。また、動作中に肩がすくまないよう首を長く保ち、胸を張るとフォームが安定します。上げきった時に肘を伸ばしきると三頭筋への収縮が強くなりますが、関節をロックするのは負担もかかるので、完全に伸ばしきらず少し余裕を持たせても構いません。フォームが固まったら15~20回を目標に実施してみましょう。
注意点
ベンチディップスは手首が反った状態で体重を支えるため、手首に不安のある方はあらかじめストレッチをしておくと良いです。動作中に痛みを感じたら中止しましょう。また肩への負担にも注意が必要です。肘を深く曲げすぎると肩関節が過度に伸展し、故障リスクが高まります。自分の柔軟性の範囲内で下げ、決して無理に深追いしないでください。特に肩を痛めた経験がある場合は、ベンチディップスそのものを避ける判断も賢明です。
負荷が物足りない場合は、足を遠くに出したり台に乗せたりすると体重負荷が増してきつくなります。逆にきつければ足をもう少し体側に引き寄せ、膝を曲げて一部体重を支えると楽になります。自分の筋力に合わせて足の位置で負荷を調整しましょう。最後に、ベンチが動いてしまわないよう注意してください。壁際にベンチを置くか、重石を載せるなどして固定すると安全です。ベンチディップスは気軽にできる半面、フォームを誤ると怪我に繋がりやすい種目です。正しいやり方で二の腕と肩を鍛え、引き締まった腕と安定した肩関節を手に入れましょう。
足の筋トレ(大腿四頭筋、ハムストリングス、大殿筋)スクワット、ブルガリアンスクワット
下半身の筋肉は体の全体の6割の筋肉を占めています。足の筋肉を鍛えることはあらゆる面に大きなメリットがあります。例えば足を鍛えることで基礎代謝が上がり、ダイエットに非常にこうかがあります。さらに足を鍛えることで足をすらっと見せることも可能です。
そして今回はスクワットとブルガリアンスクワットを紹介します。両方とも足トレの代表的な例でありその効果も非常に高いです。
スクワット
期待できる効果
スクワットは非常に効果的なトレーニング方法です。スクワットを行うことで下半身のほとんどの筋肉が使われ鍛えることができます。特に鍛えられるのは足の前側の筋肉の大腿四頭筋、お尻の筋肉の大殿筋です。この二つの筋肉は体の中で最も大きい筋肉の一つです。なのでダイエット効果などが非常に高いです。
正しいフォーム
①準備(スタートポジション)
- 足を肩幅程度に開きます。
- つま先を少し外側に向けます。
②ネガティブ動作(体を下す)
- 体をやや前傾しながら体を下します。
- 太ももの裏とふくらはぎがつくまで下ろします。
③ポジティブ動作(体を上げる)
- 足の裏の重心を意識しながらあげましょう。
- あげるときは前傾している上体をもとに戻しながらあげましょう
スクワットには様々なバリエーションがありやり方によって鍛えられる部位や効果が変わります。
例えば・・・
- お尻を引きながら体を下げることでお尻に効きやすくなります
- スタートポジションの時に足を肩幅よりも広くすると太ももの内側に効きやすくなります。
- 元の状態に戻す②の時に勢いをつけてジャンプすることでより太ももが効きやすくなります。
これをジャンプスクワットと言います。
注意すること
②で太ももの裏をふくらはぎにつくまでと記載しましたがこれが骨格上や柔軟性が足りなくてできない人もいるのでそうゆう方は無理をしなくて大丈夫です。
スクワットの動作中に背中を曲げたりすると背骨や腰に負担がかかってしまうこともあるので注意してください。痛みを感じたら動作を中断して下さい。
ブルガリアンスクワット
期待できる効果
ブルガリアンスクワットはスクワットよりも難易度が高いですがその分効果も非常に高いです。
なぜ難易度が高いのかというと片足で行うのでバランスがとりにくくなりかつ負荷が高くなるからです。
ブルガリアンスクワットは主に太ももの前の大腿四頭筋とお尻の大殿筋という筋肉を鍛える種目です。
ですがやり方によっては太ももの裏のハムストリングスと大臀筋を主に鍛えることができます。
今回はその二つのやり方を紹介します。
正しいフォーム
大腿四頭筋と大臀筋に効果のあるやり方
①準備(スタートポジション)
- 自分の膝よりも低いベンチ台を用意します。(机でも椅子でもいい)
- ベンチ台に座り軽く鍛える方の足を伸ばします
- その伸ばした足のところに立ち鍛えない方の足をベンチ台に置きます。
- 重心は鍛える方の足に8割、ベンチ台の方に2割というイメージがおすすめです。
②ネガティブ動作(体を下ろす)
- 上体を立てた状態で動作します。
- 太ももの裏とふくらはぎがつく程度まで下ろします。
③ポジティブ動作(体を上げる)
- 下ろした状態から足で地面を押す感覚で上げていきます
次にハムストリングと大臀筋に効くやり方を紹介します。このやり方は②のネガティブ動作しか変わらないのでその部分だけ紹介します。
②ネガティブ動作
- 上体を前傾した状態で下ろします。
- 膝が90度程度になるまで下ろします
注意すること
先ほども書いたようにこの種目はバランスをとるのが難しいので慣れるまでは少しずつやっていきましょう。準備運動が不足している上体でやると動作中に膝が痛くなることもあるのでその時はトレーニングをやめて少し休憩しましょう。
まとめ
初心者向けに自重でできる筋トレ種目を部位別に10種目紹介しました。胸・背中・腕・肩・脚と主要な部位を網羅していますが、いずれも特別な器具を使わず自分の体重のみで効果的に筋肉を刺激できる種目です。以下に今回紹介した種目とターゲット部位をおさらいします。
- 胸: プッシュアップ(胸全体、肩、二の腕)/ ディップス(胸下部、肩、二の腕)
- 背中: 懸垂(広背筋、上腕二頭筋、背中全般)/ Tレイズ(背中全般、姿勢改善)
- 腕: トライアングルプッシュアップ(上腕三頭筋)/ パームカール(上腕二頭筋)
- 肩: パイクプッシュアップ(三角筋前部・中部)/ ベンチディップス(三角筋前部+上腕三頭筋)
- 脚: スクワット(大腿四頭筋、ハムストリングス、臀筋)/ ブルガリアンスクワット(脚全体、臀筋、バランス強化)
自重トレーニングは初心者にとって取り組みやすく、継続もしやすい方法です。まずは自分のできる範囲で正しいフォームを習得し、少しずつ回数やセット数を増やしていきましょう。部位別に紹介しましたが、全身をバランス良く鍛えることで姿勢改善や基礎代謝アップ、日常動作の向上など様々な恩恵が得られます。実際、筋力トレーニングは心身の健康にも好影響を与え、継続することで生活の質が向上することが多くの研究で示唆されています。ぜひ本記事を参考に、自重筋トレで理想のボディメイクにチャレンジしてみてください!
最後に、安全面には十分配慮しましょう。ウォーミングアップで関節や筋をほぐし、無理のない範囲でトレーニングを行ってください。痛みを感じたら中断し休息をとることも大事です。筋トレは正しい知識とフォームさえ身につければ、必ず結果がついてきます。今日からできる自重筋トレで、筋力アップと健康な身体づくりをぜひ楽しんでください。